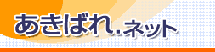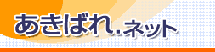原則7 外部ベンダーの活用方法
さて、中小企業の経営者の一番の悩みは「人材がいない」ことだろう。
「パソコンを活用したいけれど、社内に専門家がいない」と言うのは経営者の共通の悩みである。社内にコンピュータの専門家がいないと、どのようにシステム化を進めて良いか分からないだろうから、社長が途方に暮れるのも仕方のない所ではある。
1)ITに詳しい社員
近年、ITに詳しい人材は引く手あまただ。こう言う人材を採用しようとすると結構な人件費を払わなければならない。
一般的にシステム系の優秀な人材を採用しようとすると、最低でも年収700万円は必要だ。また優秀な人材はえてして規模の小さい会社に就職しようとはしないものだ。
だからと言って、安い月給で採用できる人材は考えものである。
例えばパソコンに詳しいだけの「システム・オタク」を、コンピュータの専門家だと間違えて採用すると、後で大変苦労する。実はコンピュータに詳しい技術者と言うのは、他人とコミュニケーションを取るのが苦手な人が多い。
子供の頃からテレビゲームに熱中し、コンピュータのプログラムを作るのは好きだが、他人との接触を嫌い自分一人で仕事したがる輩が多いのだ。こういう手合いは採用しても、なかなか会社にとけ込まず社長が大変気を遣うことになる。
優秀なシステム技術者と言うのは、どうすればコンピュータを利用して周りの人の仕事を楽にできるか、売上げに貢献できるかを常に考えている人達である。彼らにとってパソコンはあくまでも会社を良くしていくための「手段」にすぎない。そしてパソコンを利用して会社に貢献するために、積極的に周囲に働きかけ、周りを引っ張って行ける人達が、本当に優秀なシステム技術者なのだ。
だが上のような「システム・オタク」の人達にはパソコンが「目的」であって、自分が満足するシステムが出来ればそれで良い。周りを引っ張るよりも自分の中に閉じこもりがちで、でもパソコンには詳しいと言うプライドだけは高い、こんな人材を採用してしまったら後で大変後悔することになる。
2)社員をシステム技術者に育てるのは・・・
それでは、と言うことで、社員を教育して「優秀なシステム技術者」に育てるというアイデアはどうだろうか。実はこれはもっと悪いやり方なのだ。
社員が50人以上いる会社なら、システム開発部のような組織を設けて、そこに社内のシステム担当者を2〜3人配属する事は可能だろう。だがもう少し規模の小さい会社では、社員をシステム専門家に育て上げるのは止めた方がよい。
まず社員に優秀な技術者が居ない状態では、社員を教育できる人がいない。外部の研修を受講させても、なかなか優秀な技術者は育たないものだ。
さらにはITの技術は変化が大変早いため、システム技術者としての寿命は5年前後である。常に技術を追いかける努力をしないと、せっかく育てても5年位で技術者としての価値は急減してしまう。
そして一番の問題は、それでなくても人材に乏しい中小企業で、優秀な人材をコンピュータの専門家にすると言うことは、本来人材を重点配置しなければいけない部門に人が回せないと言うことである。
優秀な人材でないと良いコンピュータシステムは作れないが、社内の数少ないエースを取られてしまうと本業の方が傾いてしまうだろう。
それではどうしたら良いだろう。
3)社外ベンダーを利用しよう
それは社外の専門家を活用することだ。
例えばあなたの会社でも日々の経理処理や、期末の決算処理をされていると思う。税務や会計はかなりの専門知識が要求されるが、だからと言って社員に税理士の資格を取らせたり、外部の税理士を社員として採用したりはしないだろう。通常は外部の税理士事務所と契約して、税務相談や決算処理をお願いする。経理や税務という、自社の本業ではない部分は外部を活用するわけだ。
コンピュータも同じである。別に社内に専門家を抱えなくても、外部を上手く活用すれば良いのだ。外部のコンピュータ会社と顧問契約をするなり、必要に応じてシステム開発を委託するなりして、なるべく外部の人材を有効活用することだ。
もちろん、各社員のパソコンスキルの向上は必要である。「パソコンを使えること」と言うのはビジネスマンとしての基礎技能になりつつあるのだから
だが「コンピュータ・システムを作ること」は普通のビジネスマンには求められていない。こういう特殊なスキルが必要な部分は、外部に任せれば良いのだ。
経理でいえば、日々の精算や記帳ができる経理担当者は必要だが、毎年の税制改正の内容を熟知して決算処理や税金対策を完璧にこなせる人材を社内に抱える必要はないだろう。
コンピュータも同じである。パソコン操作ができて、自分の仕事を楽にするようなコンピュータスキルは必要だが、自社の販売システムや生産システムをどう構築するか、と言うような部分は外部のコンサルティング会社に依頼した方がよい。
経営者の悩みとして「社内にコンピュータの専門家がいないので、我が社のシステム活用はなかなか進まない」というのがあるが、これは大きな間違いである。
上に述べたように、社内に専門家を抱えるのではなく、外部の専門家を活用するのである。
だからもし経営者が悩むのなら「社外のコンピュータの専門家を頼みたいんだけど、良い会社を知らないだろうか」、あるいは「外部のITコンサル会社を活用したいんだけど、どうすれば上手く活用できるだろう」と言う悩み方が正しいのだ。
4)社外ベンダー活用のポイント
それでは次に、外部のIT専門家を活用する時のポイントについて述べてみよう。
まず外部のシステム会社の選び方だが、一番確実なのは知り合いの紹介である。
同業者、取引先、知人等から、評判の良いシステム会社を紹介してもらうのが良い。税理士事務所を選ぶ時に、知り合いから紹介してもらうケースが多いと思うが、システムの場合も同じである。
しかしながら、もし知り合いからの紹介が得られない場合は、電話帳のタウンページで「情報処理サービス」あるいは「ソフトウェア業」の分類で探してみるのも良いだろう。
そして次にシステム会社を選定する時のポイントであるが、これはずばり言って「トップの人格」である。
利用者の立場からすると、システム会社の技術力は当然として、お客さんの立場に立って色々なアドバイスをしてくれるかどうかが最大のポイントだ。そしてそれは、そう言う経営方針でそのシステム会社が運営されているかどうかによる。
だからシステム会社を選ぶ時は、あなた自らがシステム会社のトップと会った方がよい。小さいシステム会社であれば社長と、大手のシステム会社の支社であればそこの支社長と、じっくりとミーティングする機会を持ち、社長あるいは支社長の人柄や経営方針をしっかりと見極めることが大切である
そしてこの人なら我が社のシステムを任せられると思えるトップの会社と契約しよう。別にシステムだからと言って、難しい話ではない。あなたが取引先や仕入れ先とつきあう時に、この人とだったら良い仕事が出来そうだなと思う人がいるだろう。そういう気持ちをシステム会社のトップに持てれば、その会社と仕事をして失敗することはほとんどない。
私は銀行のシステム部に所属していた頃、外部のシステムベンダーさんと何度も仕事したことがある。大きいプロジェクトでは200人くらい、小さいプロジェクトでは5〜6人の技術者を派遣してもらって、銀行システムの開発を進めたのだ。
当然プロジェクトを進めるに当たって、色々な苦労があった。担当者のスキルがとても低かったり、ベンダーさんの見積もりが甘くプロジェクトが進むにつれ莫大な追加コストが必要になったり、はたまたシステムのリリース後にトラブルが頻発したり、自分の首が飛びかけた事もある。
でもどんなにプロジェクトがトラブっても、社長だったり担当部長だったり、プロジェクトの規模により役職は異なったが、ベンダーさんのトップが本当にお客さんの事を考えてくれるタイプの人だった場合、100%最後にはプロジェクトは成功した。人格的に立派なトップであれば、あらゆる困難を排してそのプロジェクトの成功に立ち向かってくれるのだ。
例えばあるプロジェクトで、システムの開発が遅れに遅れた事があった。原因は銀行側で依頼したシステム仕様が大幅に変更になったことと、ベンダーさんの見積もりが甘くて優秀な技術者を十分に手配できなかった事であった。そのプロジェクトは銀行にとって非常に重要なシステム開発プロジェクトだったため、開発の遅れは担当部長の責任問題になりかねない状況だった。
こうした状況の下、ほとんどプロジェクトをギブアップするしかないと皆が思いだした時、ベンダーの担当常務さんが「不足している技術者は、私の首を賭けても手配します」と立ち上がってくれた。そして、ベンダー社内で他部門の担当副社長と大喧嘩をしながら、技術者の手配をしてくれたのだった。後で他の人から聞いた話では、その常務さんは経営会議でその副社長の胸ぐらをつかまんばかりの剣幕で社内の説得をしてくれたらしい。
そして彼の偉いところは自社内で筋を通しただけではなく、お客さんに対してもきちっと正論を述べてくれたことだった。技術者の手配をする際に、彼は銀行の担当部長に対してこう言ったのだった。「このプロジェクトが遅れているのは事実です。しかし今更その責任をとやかく言っても仕方ありません。(プロジェクトが遅れた原因の七割くらいは、銀行側の仕様変更のせいだった)。技術者の手配は私が責任を持ちますから、御行もシステムの仕様を固められるように体制を至急整備してください。明日からX月○日までに御行の担当課長をこのプロジェクトに専念させて下さい。そして弊社の技術者と、あと二週間死んだ気で頑張りましょう」。
この提案に対しシステム部長は、その担当課長について他の仕事を全部免除して、プロジェクトに専念させた。銀行側担当者と、新しい技術者を含むベンダー側担当者、そしてその担当常務さんは、それからの二週間をほとんどオフィスで寝泊まりしながら、死に物狂いで働き、何とかシステムを予定通りカットオーバーしたのだった。
カットオーバー当日、そのシステムの紹介記事が日経新聞に掲載された。徹夜明けの朝の光の中でその記事を見た時は、思わず目頭が熱くなった。担当常務さんと堅い握手をしながら、しみじみと良い人と仕事が出来たと胸が一杯になったのだった。その記事の切り抜きは、今でも私の宝物になっている。
ちょっと話が長くなってしまったが、コンピュータという専門性の高い分野は、最後は「人」に行き着くのだ。だから外部のシステムベンダーを活用する時に、最後までお客さんのために頑張ってくれる人達かどうか、それが最も大切なポイントなのである。
←前ページへ 次ページへ→
|