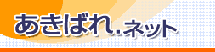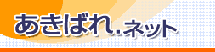原則1 社員への投資が最重要ポイント
さてここからいよいよ、企業経営者に贈る「パソコン活用に絶対失敗しない七原則」について述べていこう。
まずパソコン活用に成功するための最初のポイントは、社員への投資が最も大切だと言うことである。
1)パソコンを使いこなす人材を育てよう。
それでは例によって、自動車を例に説明しよう。言うまでもないことだが、自動車をせっかく買っても、免許を持っている人がいないと、車は運転できない。また免許を持っていても若葉マークのペーパードライバーでは、行きたいところにも行けないだろう。
つまり自動車と言う機械は、それだけでは「うどの大木」であり、それを使いこなす人間がいて初めて役に立つのである。
パソコンも全く同じで、機械だけ購入してもそれを使いこなす人がいなければ宝の持ち腐れ。誰も使いこなせないのに、まずはパソコン導入だ〜、と言うのが典型的な失敗パターンである。パソコンを導入する前に、そのパソコンを使いこなせる人を育てること、これが最重要ポイントだ。
例えばあなたが新しくタクシー会社を作ったとする。そして社員を何人か雇ったとして、しかも彼ら全員が無免許だとしよう。この場合、あなたはどのように会社を運営するだろう。
いきなり全員にタクシーを買い与え、後は自分で練習しろ、そんな経営をするだろうか。まずは、彼ら全員を教習所に行かせて、普通免許を取らせるだろう。でも免許取り立てでは、もちろんタクシーの運転手は無理だ。道も知らない、場所も知らない、そしてなにより経験不足でお客さんを乗せるには不安一杯である。そこで暫くは中古自動車でも与えて、実際に自動車を運転しながら色々なノウハウを蓄積させる。そしてお客さんを乗せられる実力がついたら、二種免許の取得にトライして、免許取得後にようやく一人前のタクシードライバーとして売上げに貢献、と言う感じだろう。
ここで言いたいのは、タクシーと言うハードを活用して商売しようと思ったら、一生懸命に人を育てないといけないこと、そして商売につながるまでにはそれなりに時間がかかると言うことである。
もうお分かりだと思うが、パソコンも同じである。パソコンと言うハードで商売に貢献したいのなら、それを使いこなす社員を長い時間かけて育てなければいけないのだ。
自動車の場合は教習所に高いお金を払って練習させて、そのあとで安物の自動車を使ってスキルアップと言う感じだろう。でもパソコンの場合は、パソコン研修にも行かせずに、パソコンだけ与えて、後は使っているうちに覚えるだろうと考える経営者が多い。でも考えて欲しい。自動車を運転したこともない人に、いきなり自動車を与えても、誰も教えてあげなければ運転なんかできないだろう。自動車をあちらこちらにぶつけて大事故を起こすのが関の山。先生なしで技術の習得なんかできないのは理の当然である。
パソコンも同じ事。パソコンに何十万円も投資しても、それを使う人に投資しなければ、ドブにお金を捨てるようなものだ。パソコンを買う前に、まずは社員の教育を行う、これが大切である。ちなみに教習所で免許を取るには、30万円前後必要だが、果たしてあなたは社員のパソコン教育にいくら位使っているだろう。
2)パソコン習得と自動車免許
しかもこれは私見だが、パソコンを使いこなせるようになるのは、自動車免許をとるよりも難しい。
車を操作するのは、三つのペダル(アクセル、ブレーキ、クラッチ)とハンドル、方向指示器、等、六〜七つの部品だけだが、パソコンのキーボードには100近くのボタンが並んでいるのである。このボタンを覚えるだけでも大変なのだ。また教習所では最低限、学科と実技で60時間前後の時間を要するが、パソコンを使いこなすにはこれ以上の練習時間が必要だ。しかも道路のルールや自動車の運転方法は一度覚えてしまえばほとんど変わらないが、パソコンの機能や操作方法はしょっちゅう変わる。つまり一度マスターしても常に新技術を勉強し続けなければならないのだ。
あれこれ考えると、パソコン技術の習得は、自動車免許取得よりもよっぽど大変なのである。
また自動車の免許を取った後、自分で実際に車を運転して、道路や場所を覚え、車線変更等の技術を身につけ、ようやく若葉マークから一人前のドライバーになって行くわけだ。言うまでもなくパソコンも同じで、通り一遍の知識ではなかなか実際にパソコンを使いこなすまでには至らない。それなりに時間をかけてパソコンのスキルを徐々にアップして行かなければならないのだ。
だから中小企業の場合、パソコンが使えない社員はまだまだ多い。また、使いこなせない経営者も多いだろう。
3)パソコン研修事例
私が以前勤めていた都銀で社内のOA推進を担当していた頃、支店長向けのパソコン研修を企画したことがある。支店を切り盛りしているミニ経営者である支店長さんの多くは五十歳前後であった。当時、パソコンを使えない中高年には未来がないと言うマスコミ論調の元、土日返上でパソコン研修に参加された支店長は真剣そのもの、ある種の悲壮感さえ漂っていた。パソコンにほとんど触った事のない彼らは、支店の中で若い行員たちが自由にパソコンを操るのを目にしながら、パソコンに対する恐れと、パソコンを使えない自分に対するある種のコンプレックスを抱えて研修に参加したのだった。
研修の目的は、細かいパソコンスキルを彼ら支店長たちに教え込むことではなく、最低限のパソコン技能の習得と、支店経営へのパソコン活用方法を教えることにあった。研修担当の女性講師たちと研修カリキュラムを検討し、テキストを制作しながら、どうすれば支店長達にパソコンに興味を持ってもらえるかを一生懸命に考えたのだった。
研修の当日、多くの支店長達は、事前に渡されたテキストにマーカーを引き、開始時間の三十分以上も前に机に整列していた。私は研修所の一番後ろで、緊張した面もちで研修を行う女性講師と、画面を食い入るように見つめる支店長達を見守った。支店長達が講師の言うことを理解できるだろうか、パソコンを嫌いになったりしないだろうか、そんな不安な気持ちで一杯だった。
でもそんな心配は杞憂だった。支店長達は初めてのキーボードと格闘し、慣れないマウスを操りながら、懸命にパソコンのことを学んでいった。女性講師の講義を聞いてパソコンを操作する彼らは、まるで学生時代に戻ったような気分だったのかもしれない。
そして全てのカリキュラムが終了した。支店長達は荷物をまとめて、席を離れた。女性講師たちは、彼らを見送るために教室の出口に整列した。今日の研修は支店長達の役に立ったのだろうか、そんな一抹の不安を感じながら。
でも多くの支店長達が、出口で女性講師の手を堅く握りしめながら、こう言ってくれたのだった。「ありがとう。パソコンとは何かが良く分かったよ」。その言葉を聞いて、彼女たちの目は真っ赤になっていた。
この時、私には分かったのだ。パソコンが嫌いな人でも、みんなパソコンが使えるようになりたいと思っていること、そしてどんな人でもパソコンは使いこなせるようになるんだ、と言うことを。
近年、中高年の失業者が増えている。ハローワークには毎日たくさんの中高年失業者が職を求めて集まっている。彼らの多くはパソコンが使えない。そしてパソコンが使えないと、良い仕事を見つけるのは極めて困難なのだ。
自社の社員をパソコンくらい使えるようにしてあげる。これは経営者として、最低限求められることかもしれない。
4)パソコン使った業務革新
さて、社員のパソコン教育はそれなりに手間ひまかかるが、ひとたびパソコンを使いこなせる社員が育てば、パソコンを活用した業務改善なんか直ぐにできる。試しにパソコンに詳しい新入社員を採用して、今までの仕事のやり方を教えてみればいい。直ぐに「こんなことも人手でやってるんですか。パソコンにやらせれば良いのに。」と言うような不満が一杯出て来るだろう。こう言う「パソコンにやらせれば良いのに」と言うのが業務改善ネタなのだ。そしてこう言うネタは、ベテラン社員がパソコンに詳しくなればなるほど、湯水のようにアイデアが湧いてくる。後はそのアイデアをどのように実現して、商売に結びつけるかが経営者の腕の見せ所と言うわけだ。
でも社員がパソコンに精通しなければ、こういう改善アイデアは決して出てこない。
だから自社の商売にパソコンを活用しようと思ったら、まずは真っ先に社員を教育してパソコンに精通させ、その後でどうすれば自分の商売を改善できるかを考えさせるのが正しい進め方である。とにかくパソコンだけ買えば、業務改善は後からついて来ると言う考えは一00%失敗する。
さてそれでは、どうすれば社員のパソコン教育を効率的に行えるのだろうか。
5)パソコン教育の進め方
まずは社員の2〜3割をパソコン研修に派遣すること。
期間は2週間程度。二週間みっちりやれば、パソコンの基礎は大体マスターできる。2週間もかけてられない、1〜2日で何とかならないのか、と思われるかもしれないが、自動車の免許と同じである。1〜2日で免許が取れるはずがないように、そんな短い期間ではパソコンは使いこなせない。ここは腹を括って2週間パソコン漬けにしてあげよう。そうすれば彼らはきっと社内のパソコンエキスパートに成長する。
そして研修から彼らが帰ってきたら、彼ら全員にパソコンを一人一台与えること。
別に最新の高級パソコンでなくても構わない。中古でも安物でも良いから、とにかく研修受講者には一人一台与えること、これがポイントである。研修から帰って来た彼らはパソコンを仕事に使いたくてうずうずしている。そんな彼らにはパソコンさえ与えれば、放っといても資料をワープロで作ったり売上げ分析したり、仕事に活用する。免許さえ取れれば後は自動車を実際に運転して上手くなるのと同じで、研修で基礎さえマスターすれば後は自分でパソコンを習得して行くのだ。
ついでに言うと、パソコンを与える時にプリンターも用意すること。紙に印刷しないと仕事には使えないから、パソコンだけでは効果が半減である。
そして彼らがパソコンのエキスパートとして成長した後は、社内家庭教師として、彼らに周りの社員の教育を担当させるのである。周りの社員がパソコンを利用して分からなかった時に、彼ら社内エキスパートに尋ねるとか、定期的に彼らエキスパートのノウハウを周囲の社員に教えてあげるとかするわけだ。
ちなみに、この社内家庭教師の割合であるが、3〜4人に1人位が限界である。
10人に1人の家庭教師では、本人が家庭教師役に忙殺されて、通常の仕事が全く手に付かなくなるか、あるいはほとんど周囲の面倒を見なくなる。社内家庭教師と言っても、自分の通常の仕事をやる片手間で周囲の人間の面倒を見るわけだから、せいぜい3〜4人の面倒見るのが限界である。
本当は社員全員が2週間研修に行くことが望ましい。従って、もし御社に余裕があるならば、時期をずらしながら全員に2週間程度の研修を受講させてあげよう。でも、もし業務多忙で全員が2週間受講と言うのが困難だとしても、必ず全員に最低「2日間」の研修は受講させよう。右に述べた社内家庭教師で、まったくの一から教えるのは相当のパワーが要求される。せめて基礎の基礎くらいは知らないと、教える方も、また教わる方も相当大変である。2日の研修に行けば、自動車で言うとハンドルと方向指示器、クラッチとアクセルの違いが分かり、簡単なカーブ位は曲がれるようになる。あとは社内家庭教師の教え方が上手くて、本人も一生懸命独学すれば、そこそこのレベルには到達するはずだ。
6)おさらい
以上色々と述べてきたが、再度おさらいすると、パソコン導入で成功するためには、パソコンのハードではなく、それを使いこなす社員の教育に投資することが最も重要なポイントである。
そして教育に際しては、社員の二〜三割に二週間程度の研修を受講させ、社内のエキスパートとして養成して行く事が大切なのだ。
←前ページへ 次ページへ→
|